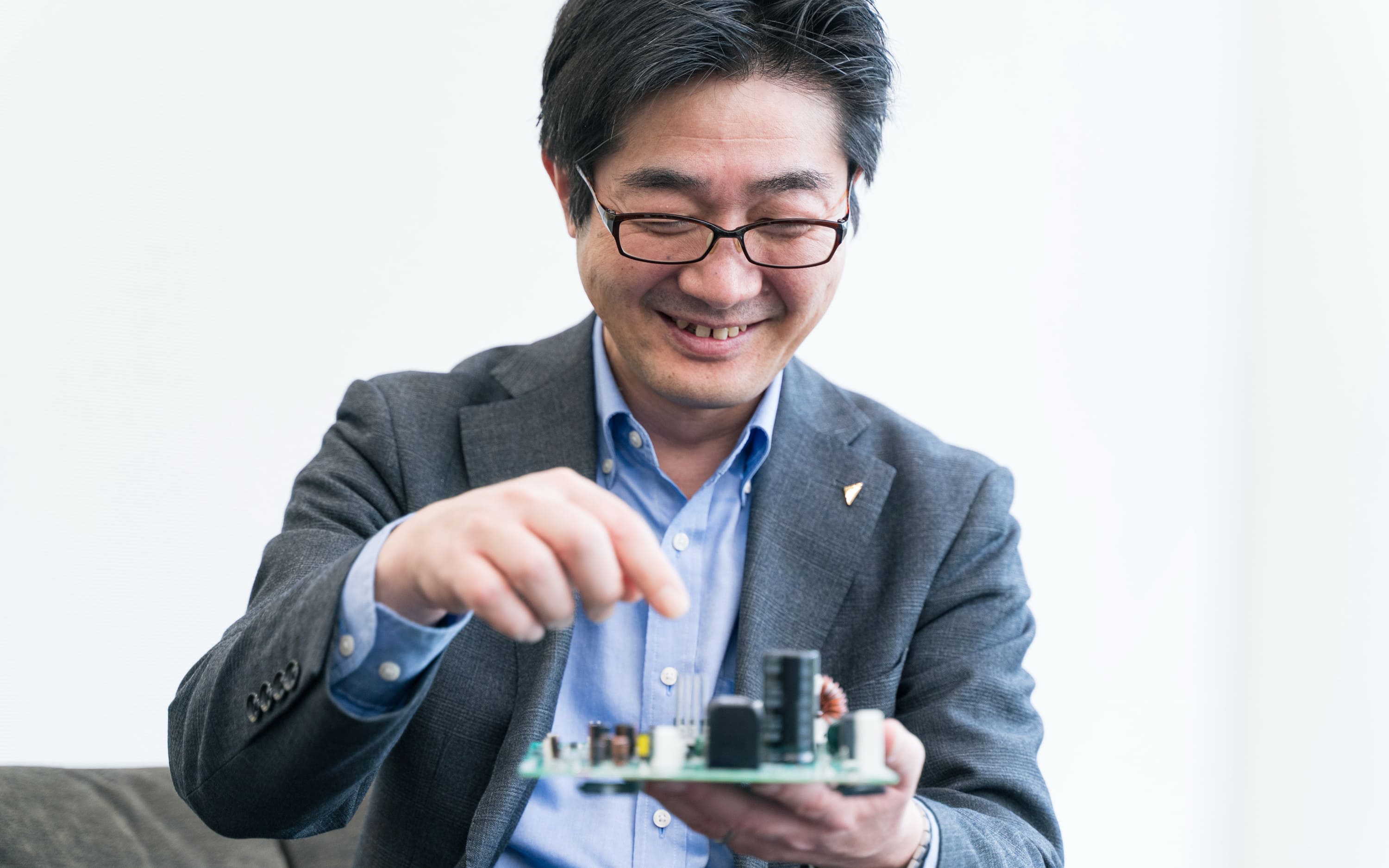そこで思い切って東京支社(東京都中央区八重洲)にTIC東京分室を設置し、技術リサーチ活動・ベンチャー協業を行うとともに、実験ができる技術開発拠点として東京ラボを設置しました。これにより、大学との共同研究やベンチャー企業との連携、新卒・中途採用でも大きなメリットを得ています。
そこで思い切って東京支社(東京都中央区八重洲)にTIC東京分室を設置し、技術リサーチ活動・ベンチャー協業を行うとともに、実験ができる技術開発拠点として東京ラボを設置しました。これにより、大学との共同研究やベンチャー企業との連携、新卒・中途採用でも大きなメリットを得ています。
 東京ラボの多用途に対応できるエリア設計
東京ラボの多用途に対応できるエリア設計ーー空調機を差別化するカスタム半導体
松井:ダイキンが半導体開発を進める最大の強みは、空調機全体を俯瞰しながら進められることです。高効率の空調機を実現するためには、「独自の制御方式をいかに半導体上で具現化するか」が重要になります。とくにモータ制御においてはダイキンならではのノウハウがあり、それを半導体として実装することが他社との差別化の鍵になると考えています。
 TIC東京ラボではインバータ他主要部品の半導体開発に取り組む
TIC東京ラボではインバータ他主要部品の半導体開発に取り組む
入社当初に配属された部署では、EMCの評価環境がすでに整っていたので、改良はあっても大まかな手順や装置が備わった状態でした。しかし東京ラボでは、何もないところから自分たちの使いやすいように設備を導入し、アプリケーションを開発できるため、大きなやりがいを感じています。半導体評価技術の立ち上げは大変でしたが、ゼロから取り組む分、完成したときの達成感は格別でした。
堀之内:汎用品では実現できない機能を組込んだカスタム半導体を開発すれば、他社との明確な差別化が可能になります。空調機へのカスタム半導体導入はまだ一般的ではありませんが、自動車や産業機械では既に活用が進んでいます。半導体を自社開発することで内部構造や動作を深く理解し、半導体メーカーと対等に議論できるようになれればと思っています。
――カーボンニュートラルとウェルビーイングへの貢献
松井:カスタム半導体開発は、インバータの性能向上による省エネや機器の小型化、材料費の削減など、カーボンニュートラルにつながる取り組みです。
岩田:世界ではまだインバータを搭載していない空調機が多く稼働しており、2050年までに電力需要が3倍に増えるという予想もあります。その中で、高効率なインバータ搭載空調機の普及が強く求められています。
堀之内:東京には多数の大学や企業が集まり、情報交換や協業の機会が豊富です。そうしたネットワークを活かし、より優れた素材の採用やさらなる小型化をめざして、エネルギー効率の向上に取り組んでいきたいと考えています。



ソフト/ハードにこだわらない横断的な設計技術を磨き、世の中のニーズに応えていきたい。