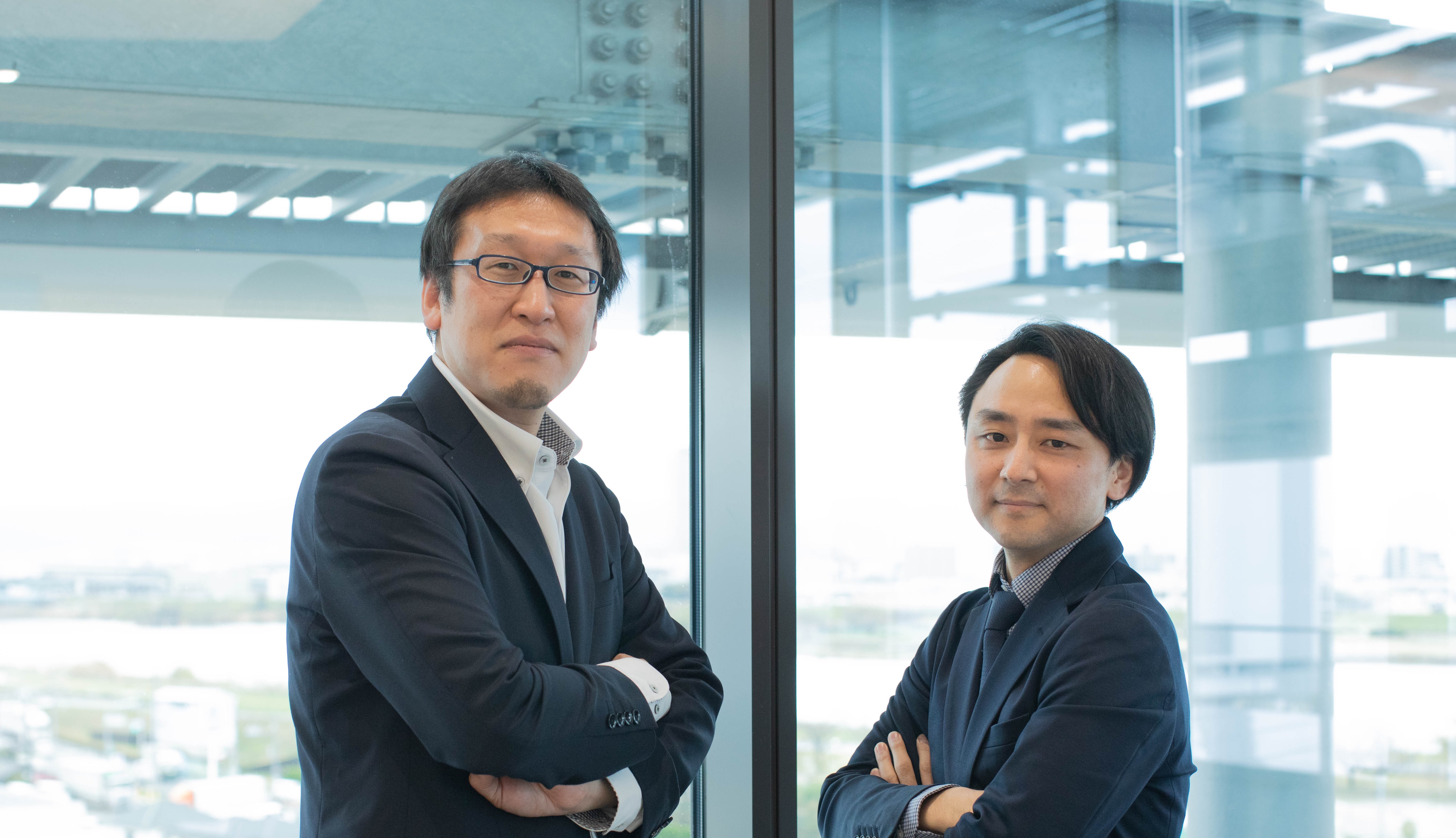堀:具体的な効果(数値)については実証実験を行わないと分かりませんが、これまでに十分なシミュレーションを行っており、効果を期待できるものだと考えています。これは一般的なデータですが、室内には1日2,000万個の花粉が侵入し、その原因の約60%が換気によるものだといわれています。換気による花粉を極力ゼロに近づけることが、今回掲げている開発目標です。
ちなみに残りの40%は洗濯物への付着や、着ている衣服への付着による持ち込みです。これについては、空調機だけではできない部分ですので、Toyota Woven Cityの住民の皆様のライフスタイル、例えば洗濯物の干し方、外出のタイミングなど、についてコミュニケーションを取りながら無理のない対策を考えていきたいと思っています。
パーソナライズされた機能的空間。快適性と機能性を両立する空間とは
ーーパーソナライズされた機能的空間とは何か
中川:リラックスや集中、あるいは快眠など、人にはさまざまな状態があります。「パーソナライズされた機能的空間」は、そのような状態を空気と他の要素を組み合わせて作るパーソナルな空間です。
まず、空気は当社が得意とするところです。温度や湿度、気流、それに清浄度といった空気の要素を組み合わせて、日々の生活シーンに合わせた空間を作ります。一例として、過去には「point 0 marunouchi」という東京・丸の内にあるコワーキングスペースにおいて、他社様との協創で軽井沢の心地よい自然風を再現する気流コントロール技術を開発しました。

さらに、Toyota Woven Cityの実証実験では空気の要素に加えて、映像や音、それに香りや照明などを組み合わせて最適な空間になるような調整を行います。例えばリラックスしたいときには軽井沢や尾瀬をイメージするような高原の映像や音、それにリラックス効果があるとされるラベンダーの香りを組み合わせます。
もちろん個人差は考慮しますが、人に共通するパラメータもあります。共通部分をきちんとおさえたうえで、パーソナルに調整できる仕組みを、実証実験を通して構築していきたいと考えます。
――効果の評価方法
中川:リラックスや集中などの感想は個人差が大きく、一つの数値のみで評価するのが難しい分野です。アンケートを実施したり、多感覚な機能空間の内外においてタスクの遂行時間を測定したりと、様々な側面から評価したいと考えています。
一方、空気の要素の効果については社内で蓄積したデータがあります。これらのデータを活用しつつ、空気要素だけの場合と、その他の要素を組み合わせた場合の有意差についても評価し、空気が持つ価値を明らかにしていきたいと考えています。
Toyota Woven Cityだから得られる実生活からのフィードバック
――Toyota Woven Cityで実証実験をする意義
堀:Toyota Woven Cityという実際に人が住む環境で、長期間にわたってデータを得られるのは非常に大きなメリットです。花粉症は季節性があるのはもちろん、黄砂やPM2.5など他の要素によっても症状の度合いが変化することもあります。こうした状態(データ)を連続的に取得できるのは非常に良いことです。データが多すぎて分析が難しいところもありますが、ウーブン・バイ・トヨタさんの力も借りつつ、ダイキン情報技術大学出身のメンバーにも入ってもらい、数式モデルに落とし込みたいです。
――Toyota Woven Cityの住民
王:Toyota Woven Cityには、発明家マインドを持つ住民が集まります。その住民の方々からは、実証であることを前提とした様々なフィードバックや思いもよらない提案が期待できます。それを商品開発に展開することにより、スピーディーかつ確かなビジネスを構築できると考えています。
中川:パーソナライズされた機能的空間の実証実験を進めるうえでも、Toyota Woven Cityの環境はとても重要です。リラックス、集中、快眠といった求める効果や、それを実現する要素の組み合わせはさまざまあり、ターゲットによっても変わります。技術者だけでなく立場の異なるご家族の方がいることで、多方面から率直なフィードバックが期待できるのではないかと考えます。
――Toyota Woven Cityだからこそ実現できるデジタルツイン
堀:Toyota Woven Cityはリアル空間の実験と、デジタル空間のデータが非常に強く結びついた場所だと理解しています。その場で起こっている現象を自分の目で見られるだけでなく、どのようにデータに表れるのかすぐに分かるため、カイゼンのサイクルを早められたり、シミュレーションの精度を向上したり、などさまざまなメリットが期待できます。

スギ花粉だと飛散時期の約2か月が勝負です。分析から実装のサイクルを早めて、この間に勝負できる回数を増やすことで、開発にかかる時間が年単位で変わってきます。また、既にデジタルのToyota Woven City(※1)が存在しているようですので、各所に設置予定のセンサー情報と掛け合わせることで、少ない手間で、高精度に花粉がどう侵入してきているかなどをシミュレーションできるようになると、期待しています。
社会実装に向けて
――協創の可能性
堀:「花粉レス空間」の開発において、現時点において協創は考えていません。しかし、私たちが提案するソリューションを世の中に広めるためには、ハウスメーカーさん(戸建住宅)やデベロッパーさん(マンション)など人の暮らしに近い業種との協創は将来的に必要だと考えています。
中川:「パーソナライズされた機能的空間」においては、空気以外の要素の構築には他企業様との協創が必要であると考えています。今後に期待していただければと思います。
――今後のビジョンと、海外も含めた展開の可能性
堀:さらなる事業貢献に向けて社会実装する計画のもと「花粉レス空間」のプロジェクトを進めています。今後の展開として、花粉症の多い国内だけでなく国外もターゲットとして考えています。そのときは花粉レスではなく、別の◯◯レスかもしれません。
空調は各国で文化が異なりますし、空間となると建物側とのすり合わせも必要なので、これまで以上に社内外の協創による地域に合わせた形での実装が求められます。技術開発のコントロールタワーとしては国内外の戸建て住宅やマンションに導入しやすい花粉レス空間の基準を確立し、機器単体の販売から、システム販売、空間提案にまで広げていきたいと考えています。

王:花粉症というと、薬、マスク、メガネが一般的な対策ですが、今回の実証実験を通じて、実は空調システムも重要であるということを広めていきたいと思っています。ですが、実証で良い結果が得られたとしても、換気装置って建物を建てるときぐらいしか考えないので、多くの人にすぐに届けるのが難しいんですよね。
まずは、空調システムによる花粉対策に感度が高いお客様をターゲットに今回の花粉レス空間を実装し、その効果を世の中に認めもらいつつ、他の多くのお客様が自宅に簡易的に導入できるような新たな花粉レス空間の開発にもつなげていきたいです。

中川:「パーソナライズされた機能的空間」も2030年を目処として社会実装を目指しています。住宅やビルといった建物だけでなく、様々な空間に対する価値の拡張を実現したいと考えています。
Toyota Woven Cityそのものが海外からも大きな注目を集めているプロジェクトであり、そこに参画する当社のソリューションも同時に注目されることを期待しています。